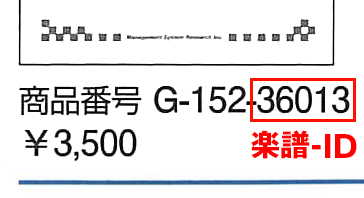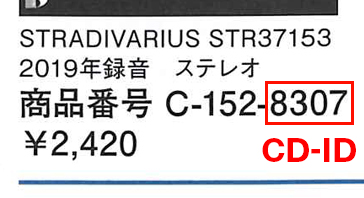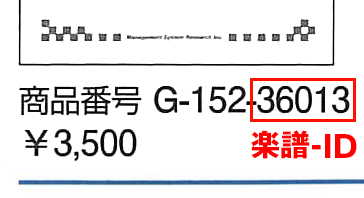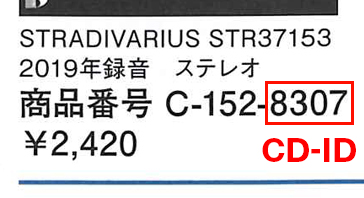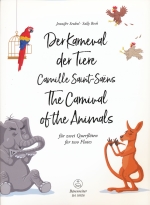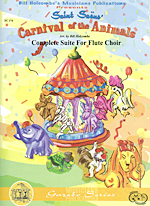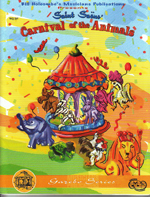�����w�|��w�����̐����a���搶�Ɏ��M���Ă��������܂����B
�����̋L����2021�N�Ɏ��M���Ă������������̂ł��B
��5��́A���̔g���̒��Ő��ݏo���ꂽ�w�����̎ӓ��Ձx�ƁA��87�N��w�f���}�[�N�ƃ��V�A���w�ɂ��J�v���XOp.79�x�ɂ��Ă��b���v���܂��B
�������[�O�i�[�ĂI
������鎄�����ɂƂ��āA���t��œ{������ь����Ƃ��������Ƃ͑z��������Ƃł����A19���I�㔼�ɑ傫�Ȃ��˂�ƂȂ������O�l���Y���ɂ́A���̂悤�ȓ��قȈ�ʂ�����܂����B
1883�N2��13���A���[���b�p����Ȍ������������[�O�i�[���S���Ȃ�ƁA���̎��������ă��O�l���Y���̉��͒��É�����ǂ��납�A��w�̌������𑝂��܂��B
����Ȓ��A�T�����T�[���X�́w�n�[���j�[�ƃ����f�B�[�x�Ƒ肳�ꂽ1���̖{�̕Ҏ[���J�n���A���̏������ȉ��̕��͂Ō��т܂��B
���̓��[�O�i�[�̍�i���A�������������������S�ꑸ�h���Ă���B
�D��Ă��ė͂�����A���ꂾ���ŏ\���Ȃ̂��B
���̓��O�l���A�����ɑ��������Ƃ͂Ȃ����A���ꂩ��������Ȃ����낤�B
�}���n�[���j�[�ƃ����f�B�[�ɊW���Ȃ����[�O�i�[��_�����悤�ȏ����ł����A1885�N8�����{�Ɋ��s�����ƁA���̒������h�C�c�����̋t�ɐG��A���N�̃h�C�c�E�c�A�[�͑�g���ƂȂ�܂��B
�h�_���r�߂�T�����T�[���X�I
�k�t�����X�A�A���X�Ɏn�܂�R���T�[�g�E�c�A�[�́A1886�N�P��22���Ƀx�������E�t�B���n�[���j�[����̌������}���܂��B
�T�����T�[���X������ɓo�ꂷ��ƁA���O�͑҂��\���Ă������̂悤�ɋ��ѐ��A���J�A���J���錾�t�Ȃǂ����������т������A���ɂ͌x�@��������鎖�ԂɎ���܂��B�T�����T�[���X�͉��t����萋���A����������J�b�Z�����������Ƃ��܂����A�J�b�Z����������̎x�z�l����u�T�����T�[���X���h�C�c�̉��y��|�p�ɑ���G�ΓI�ȑԓx���Ƃ����A�ނ̖��O���L�����v���O�����ւ̎Q������؋��₷��v�Ə����ꂽ�莆���͂��A�h�C�c�����̌����悪�����݃L�����Z���ƂȂ�܂��B
�h�C�c�ł̃c�A�[��f�O�����T�����T�[���X�͎��̌�����v���n�������܂����A�����ł����̗]�g�������̉������������܂��B�������h�C�c�Ƃ͏��قȂ�t�����X�ɐe�a�I�ȃ`�F�R�i�����̓I�[�X�g���A���n���K���[�鍑�j�́A�T�����T�[���X�Ɍh�ӂ��A���E�ōł�����������̂ЂƂƂ����鍑������ő������p�ӂ��܂��B
�N���f�B����

�N���f�B���̊X����
�N���f�B���i���݂̃`�F�R�j�ƃT�����T�[���X�Ƃ̊W��4�N�O�ɑk��܂��B1882�N1��22���̃v���n�������̍ہA�T�����T�[���X�̓N���f�B�����w����痧�h�ȉԗւ����悳��A�N���f�B������̔h���c�ƗF�D�W��z���Ă��܂����A
����̕\�h�K��͂��̉��ɂ����̂Ǝv���܂��B
���̃N���f�B���ƁA����w�����̎ӓ��Ձx�a���Ƃ̊֘A���w�E��������������݂��܂����A���̌��ɂ��ẮA�㔼�̐����T��ŏڂ����q�ׂ����Ǝv���܂��B
�t���X�g�Ƃ̕ʂ�
�T�����T�[���X�A�^�����F�߂�ꂽ��
5��19���A�T�����T�[���X�͌����ȑ�3�� �n�Z�� Op.78�s�I���K���t���t�������h���̃Z���g�E�W�F�[���Y�E�z�[���ŏ������A��1887�N1��9���ɂ̓p�����y�@���t����Ńp���������}���܂��B
�T�����T�[���X���g�u����Ȑ^���͓�x�Ƃ��Ȃ��v�Ƃ����قǑS�Ă��������̌����Ȃɑ��A�V������ł́u����قǔM���I�Ȕ���𑗂��Ă���̂��������Ƃ��Ȃ��v�u���̂悤�ȉ��l�̂�������Ȃ��p���Œ����ꂽ�̂́A�����f���X�]�[���ȗ��ł͂Ȃ����v�ƕ]����܂��B
�T�����T�[���X�ɔᔻ�I�ȕ]�_�Ƃ�O�l���A���@���Ɋւ�炸�A�L���������킳�ʈ��|�I������ڂ̓�����ɂ����t�����X�������A���ɃT�����T�[���X�̐^����F�߂��̂ł��B
�������y����E��
1871�N2���ɃT�����T�[���X�����S�ƂȂ�ݗ������������y����́A�u���ݐ����Ă���t�����X�l��ȉƂ̍�i�Ɍ���v�u�F���I�ɁA���g�I�ɂ��݂��������������Ɓv�Ȃǂ��m�F����ݗ�����܂������A����ɉ�ɔ������o������Ƃ̊Ԃ��a�݂������n�߂܂��B
1886�N11��21���ɊJ�Â��ꂽ����ŁA���O�̍�ȉƂ̍�i�������グ��Ƃ����ӌ����̑��A�Z�U�[���E�t�����N����ɐ��E�����ƁA�T�����T�[���X�͒ǂ���悤�ɍ������y�����E��܂��B
���V�A����

�A���N�T���h��3���ƃ}���A�E�t���[�h�����i
�����ȑ�3�ԁs�I���K���t���t�p����������n�܂闂1887�N�͕����ȔN�ƂȂ�܂��B4���A�T�����T�[���X�̓t�����X�ԏ\���Ђ̎x���ɂ�郍�V�A�����ɏ��҂���A�t�����X���ւ�NJy��̖���^�t�@�l���A�N�����l�b�g�̃V�������E�g�D���o���A�I�[�{�G�̃W�����W���E�W���̋����҂ƂƂ��ɁA
�T���N�g�y�e���u���N��7��̌������s���܂��B
4��21���A���̃c�A�[�̂��߂ɗp�ӂ��Ă����t���[�g�A�N�����l�b�g�A�I�[�{�G�ƃs�A�m�̂��߂�
�w�f���}�[�N�ƃ��V�A���w�ɂ��J�v���XOp.79�x���������A���V�A�c��ɉł����f���}�[�N�o�g�̍c�@�}���A�E�t���[�h�����i�Ɍ��悵�܂��B
���t����12�����x�̂��̍�i�ɂ́A�₩�ȏ��t�̌�Ɍ����R�̃A���A�ɂ��ꂼ��f���}�[�N�ƃ��V�A�̉̂��p�����Ă��܂����A
�ꍑ�̐���������邽�тɂ��݂������߁A���ݍ����c��ƍc�@�̎p���ڂɕ����Ԃ悤�ł��B����Ɋe�e�[�}�ɑ������@���G�[�V�����ɂ́A�e���̃e�[�}���d�Ȃ荇���u�Ԃ�����܂����A����͍��ƍ��̌q����A�܂�u�F�D�v�����킳�ꂽ�Ƃ��ǂ݂Ƃ�܂��B
�O�N1886�N�̓h�C�c�����ɂ͂��܂荑�����y����E��Ȃǖ|�M���ꂽ�N�ł����̂ŁA�T�����T�[���X�͂��̃J�v���X�ɁA�Z�a�╽�a�ւ̑z�������ߍ�Ȃ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����T��A�N���f�B�����ɒ��ށI

�V���������W���Z�t�E���u�[�N�i1822-1893�j
�ł́A�w�����̎ӓ��Ձx�ɖ߂�܂��B
���ݏ��w�Z�̉��y�̎��Ƃł��悭���グ����قǃ|�s�����[�Ȃ��̍�i�ɂ́A���{��ŏ����ꂽ�����̉�����݂邱�Ƃ��ł��܂����A�u�N���f�B���ō�ȁv�u���u�[�N�P��̉��t��ŏ����v�u�N���f�B���̎ӓ��Ձi�}���f�B�O���̓��j�ʼn��t�v�Ƃ������L�q���U������܂��B
�܂�w�����̎ӓ��Ձx�̒a���ɃN���f�B�����[���ւ���Ă��邱�Ƃ��q�ׂ��Ă���̂ł����A�����̐V����R�����ƁA
�t�����X�̐V���Ɍ����L��������̂ł����A
�v���n�̐V���ɂ͂��̍��Ղ��ЂƂƂ��Ă݂��邱�Ƃ��ł����A����������Ȃ⏉���n�̓N���f�B�����낤���H�Ƃ������^�O������܂��B
����̐����T��́A�N���f�B���Ɓw�����̎ӓ��Ձx�̊W�ɂ��ĉ��������������Ǝv���܂��B
�@�T�����T�[���X�̍s�������ɂ���
�悸�̓T�����T�[���X�̍s���𒀈�Ă���v���n�̐V��Dalibor���𒆐S�ɁA�v���n�����̃X�P�W���[�������Ă݂܂����̂ŁA�y�����ڒʂ����������B
- 2��1����
- �v���n����
- 2��9���t
- �f���������̎莆�u���x�̃}���f�B�O�������̂��߂ɑ�^�̍�i�i�����̎ӓ��Ձj���������Ă���Ƃ���ł��c�o�ł������ɂ������ł��B�v
- 2��13��
- Čeňka Mieka���i������������̋��s�ҁj�̃T���������@
- (13 or 14��)
- �v���n�˃N���f�B��
- 2��14��
- �N���f�B���̌���ʼn��t
- 2��15��(��)
- �N���f�B������v���n�ɖ߂�A�w�ō�����������̃v���O��������Ǝ�z
- 2��19��
- ����������� 19���J�� �w���ƃs�A�m�Ƒt
- 2��21��
- �v���n�˃E�B�[��
- 2��23��
- �E�B�[������v���n��Dalibor�����ĂɎ莆
- (���t�s��)
- �T�����T�[���X���͂���ȃ��Z�v�V�����J��
- (���t�s��)
- �E�B�[���˃I�[�X�g���A�̏����Ȓ��i�N���f�B���H�j���̒��ɐ������Ă�w�����̎ӓ��Ձx�������グ��B
- 3��6�`9��
- �ӓ��Ղ̊���
- 3��9��(��)
- �w�����̎ӓ��Ձx�����@���F���u�[�N�P��̉��t��
�X�P�W���[�����炨����̂悤�ɁA�T�����T�[���X��2��14���Ɉ�x�N���f�B����K��Ă��܂���
�i�O���u�N���f�B���ցv�Q�Ɓj�A���̖K��Ɓw�����̎ӓ��Ձx�ɂ͊֘A�������Ǝv���܂��B
�A�{���ɃN���f�B���ō�ȁH
���{��̑����̉���ɂ́u�N���f�B���ō�Ȃ��ꂽ�v�Ƃ���܂����A��{�ƂȂ鎑���i�{�k���A1922�j�ɂ́u�I�[�X�g���A�̏����Ȓ��v�Ƃ����L����Ă��炸�A���ꂪ�N���f�B�����w���̂��܂ł͎����Ă��܂���B���m�̎�v�����́A�����Ȃׂă{�k���ɏy�����L�q�����Ă���悤�ł����A�u�����Ȓ��v�����ł��邱��ȏ�̎������������߁A��Ȓn�ɂ��Ă͒f��ł��Ȃ��Ƃ����܂��B
�����A������Ȓn�ł���Ƃ���A�E�B�[�������250�L�����̋����ɂ���N���f�B���ɍēx�����߂������ƂɂȂ�A���s���I�ȕs���R���͊o���܂����A�T�����T�[���X�ɐe�a�I�ȓ��n�̌��ӂɂ��A���������č�Ȃł���ꏊ����ꂽ���Ƃ��l�����܂��B
�B���u�[�N�P��̌����Ƃ́H
�u���u�[�N�P��̌����v�𑽂��̕��́A�N���f�B�����������ŁA���n�ɏ����̂��郋�u�[�N���J�Â��Ă�������Ɨ������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����n��m�邽�߂ɂ́A�悸���u�[�N�Ƃ����l���Ɓu�P��̌����v���̂ɂ��Đ������m��K�v������܂��i�l���ɂ��Ă͒����������������j�B
���u�[�N�̍P������́A���炭1874�N2��17���̌����iHerz�z�[���F�p���j���n�܂�Ǝv���܂����A�ȍ~�}���f�B�O���̓��i�ӓ��Ղ̍ŏI���j���z�[�������_�Ƃ��p�����Ă��܂��B�܂�u���u�[�N�P��̌����v�Ƃ́A�p�����������Ӗ�����̂ł��B
�C�{���ɃN���f�B���ŏ����H
�N���f�B���������𗠕Ԃ�����I�؋����ALe Menestrel���i3��7�����j�ɂ݂��܂����B�����ɂ́A�T�����T�[���X�������̒����Ȃ�����h�C�c�E�c�A�[����A���������Ƃ��L�ڂ���Ă��܂��B�܂�ӓ��Պ��Ԃ�3��7���ɂ̓p���ɋ��邱�Ƃ���A�N���f�B���̎ӓ��Ղŏ������ꂽ�Ƃ������͔ے肳��܂��B
�p���̎ӓ��Ղʼn��t������i���A�A�H�̓r���ɗ���������I�[�X�g���A�̏����Ȓ��i�N���f�B���H�j�ō�Ȃ��A�A����Ƀp���ŏ��������Ƃ������Ƃ��^���̂悤�ł��B
�Ō��
�ł́A�Ō�Ɂw�����̎ӓ��Ձx�̉��t�|�C���g�ɂ��Đ����v���܂��B
���̂悤�ȃG���^�[�e�C�����g���̋�����i�͒P�ɏ��ɉ��t���邾���ł͂Ȃ��A���ꂼ��̊y�Ȃ̓�������������A��ҕ��ɂ����u�L���������v���Ƃ��|�C���g�ł��B�^�t�@�l���͍ĉ��̍ہA�����̔�蕨�����ďo�������悤�ł����A�z�[���ɋ��Ȃ���ɂ��Ċy�����������ɗU���A����ȉ��t���ł�����f�G�ł��B
1�Ȗځu���t�Ǝ��q���̍s�i�ȁv�`���A�����Ȃ��5�x�i��3���������S5�x�j�̃g����������n�܂�܂����A�悸�͂��̋ȋ����Œ��������u�ŕs�v�c�ȋ�ԂɗU���A���̌㑞�X�������C�I�����ڂ̑O�Ƀk���ƌ���܂��B���܍������ޕS�b�̉����C�I���̗Y���уK�H�`�`�I�I�ŁA�����Ԃ�^�������O��k���オ�点�ĉ������B
2�Ȗځu���{�ƗY�{�v�́A���݂��̎咣���܂���������Ȃ���łȕv�w�I�H
3�Ȗځu途n(���o)�v�͋��������o�Ɣn���������킵�����G��B���͑������\�V�C�ȃ��o�����������˂�����B�������g�s������ړI�������炸��...
4�Ȗځu�T�v���ЂƂ��Ƃŕ\���Ȃ�u�^����̉��y�̃X���[�Đ��v�B �p���f�B�[�̖��l�ɂ̓I�b�t�F���o�b�N�����܂����A�T�����T�[���X�������Ă͂��܂���B�Ȃ�ƃT�����T�[���X�́A�I�b�t�F���o�b�N�́w�V���ƒn���x�i�n���̃I���t�F�j�������f�B�[�͂��̂܂܂ɁA�e���|������ς���Ƃ�������@��p�����̂ł��I�@�����l�C�Ⓒ�ł������I�b�t�F���o�b�N���A�p���f�B�[�Ԃ��������́u�T�v�B�������ɂ͕�����|�������͂� �B
���Ȃ݂ɁA���w�Z�̉^����ōL���g�p����Ă��邱�́u�n���̃M�����b�v�v�A���̓L���o���[�Ȃǂŗx����t�����`�J���J���̗��s�C������\�����ʖ��u�J���J���v�ȂǂƂ��Ă���i�B�J���J����m���Ă��邨������͉��ĕs�ސT�ȁI�ƁA���ꂱ���J���J���ɓ{��̂ł́I�H

��
5�Ȗځu�ہv�̃|�C���g�́u�M���b�v�G���v�ł��B�ۂ��m�b�V�m�b�V�ƕ����l��`�����T�����T�[���X�̃I���W�i���E�����f�B�[�ɑ����A�x�����I�[�Y�́w�t�@�E�X�g�̍����x�̒��́u�d���̗x��v�A�����f���X�]�[���́w�^�Ă̖�̖��x�́u�X�P���c�H�v��2�Ȃ�����܂��B ���̍�i�́A�ۂ��d���H�Ƃ������M���b�v�����T�����T�[���X�����߂����́B�܂�A�B�҂ɉ��t������A�ނ����⊾�����������u�L�b�`���ɉ��t���ׂ��ȂȂ̂ł� �B
��͒����̂Œ[�܂�Ȃ���������܂��B
7�Ȗځu�����فv�͐l�C�̂Ȃ��V�`���Ƃ��������ق̕Ћ��ɒu���ꂽ�����ɁA�Ƃ�����u�N�u�N�b�ƖA�����l�q�B���́u�u�N�u�N�b�v�ɁA�Î��j���Ă��܂����\����Ȃ��A㵒p�S�Ƃ��������킢����������Ȃ��f���炵���B
10�Ȗځu�傫�Ȓ��āv��Volière�Ƃ������t�ɂ́u������ׂ�̗��܂��v�Ƃ������Ӗ�������悤�ł��B�b�������A�����ň���I�ɂ���ׂ葱���遛������Ƃ����������ł��傤���B�Ō�̃N���}�e�B�b�N�̃f�B�~�k�G���h�����ꂢ�Ɍ��܂�A�u���h�A���͖̂����������Ƃ�...�v�Ǝp�������Ă�����������̌��e���݂��邩���B
11�Ȗځu�s�A�j�X�g�v�͂������������ł��傤���i�L�`�I�ɂ͓����ł���...�j�H�@��S�s���ɓ����l���u�����o�`�v��u�G�R�m�~�b�N�E�A�j�}���v�Ə̂��邱�Ƃ�����܂����A�T�����T�[���X�̓s�A�m�Ɍ������ĂЂ�������K����s�A�j�X�g���ɕ��ނ��܂����B
���݂ł͈Ӑ}�I�ɏc�̐������炵�A�ӂ�ӂ�e�����t���嗬�ƂȂ��Ă���悤�ł����A���̃A�C�f�A�̓T�����T�[���X�v��ɏo�ł��ꂽ�f�������̏��ŕ��̒��ӏ����u���t�҂́A���S�҂̔@���������Ȃ��i�ҏW�Ғ��j�v�����ƂȂ��Ă���悤�ł��B���ꂪ������Ȏ҂̎w���ł���T�����T�[���X�̖��O�������͂��ł����A�u�ҏW�ҁv�܂�f�������̌��t�Ƃ��ċL���Ă��܂��B
���M���ɂ͂��̎w�����Ȃ��A�����ʂ����R�Ƃ��Ă��邱�Ƃ���A�T�����T�[���X�́A�ނ���@�B�I�Ȑ��m���Ɩ��_�o�Ȃقǔς����ŗ��K���閳�@���ȉ��t��z�肵�Ă����̂�������܂���B
������ɂ�����ȃs�A�j�X�g�����S�ҕ��ɉ��t���邱�Ƃ͈ӊO�Ɠ�����́B
�ǂ����@���v�����܂����I�@�E��ƍ�����t�ɒe���Ƃ�...

����
13�Ȗځu�����v�̓T�����T�[���X�̊��S�Ȃ�I���W�i���ŁA慎h�ł͂���܂���B���������������A�����Ĕ������B
14�Ȗځu�I�ȁv�ŋ��߂���̂͂܂��ɂǂ���B�܂�ŋg�{�V�쌀�̂悤�ȁB�Ō�ɂ��ׂĂ̏o���҂����낢���݂��A�ǂ���Ńt�B�i�[�����}�����ʂ͎Q�l�ɂȂ�܂��i���Ȃ݂Ɏ��̓h���t�h�ł���...�j�B
���̑g�Ȓ��t���[�g���W�����i�́u�����فv�u�傫�Ȓ��āv�u�I�ȁv��3�Ȃł����A�u�傫�Ȓ��āv���t���[�e�B�X�g�ɂƂ��Ă̍Г�A���Ƃ��œ�ցB
�����g���x���S�ȉ��t���������Ƃ�����܂����A�u�傫�Ȓ��āv�Ɏ���܂ł̐��_��Ԃ�����͂���͂���...
�f���}�[�N�ƃ��V�A���w�ɂ��J�v���X Op.79
���� �a��
�����Y�p��w�ɂăt���[�g���������A�א쏇�O�e���Ɏt���B�W���l�[�����y�@�ɂă}�N�T���X�E�������[���Ɏt�����v���~�G�E�v������܂��C���B����܂œ��{�؊ǃR���N�[�����I�̑��t�����X�A�C�^���A�̃R���N�[���ɂē��܂���B�A����͐��E�e���̉��y�Ղ��w��菵�ق��A�}�X�^�[�N���X�A�������s���B2019�N�A�}�N�T���X�E�������[���Ɛ��E�����[�c�@���g �I�y�� �f���I�S�ȃ��R�[�f�B���O���s���A�t�����XSkarbo��胊���[�X����B2012�N16�N�ɂ̓C�^���A�ŊJ�Â��ꂽ�Z���F���[�m�E�K�b�c�F���[�j���ۃt���[�g�R���N�[���R�����߂�i��5��͐R���ψ����j�B
���݁A�����w�|��w�����A���{�NJy�|�p�w�����B