フルートを愛する人に、愛されるフルートを。
商品ID検索
商品や季刊誌に記載されている「楽譜ID」と「CD-ID」で商品を検索する事ができます。
メンバーズ・クラブ「フルート・インフォメーション」記載の商品番号で検索する場合は、最後のハイフン以降の番号で検索してください。
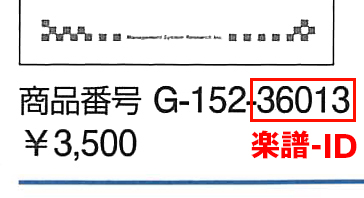
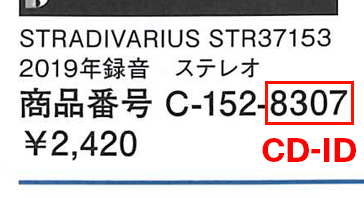
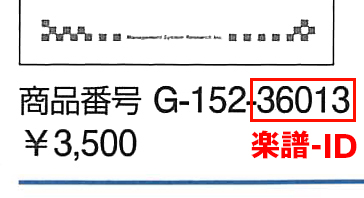
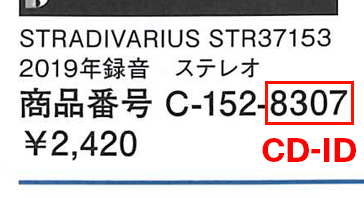
もがりぶえ
2.空襲警報
第二次世界大戦末期、1944年の10月1日から翌年の8月17日迄、僕は上野の音楽学校から出向のような形で、同窓の友達14名と共に陸軍戸山学校軍楽隊の隊員となった。一緒に上野から軍楽隊に入った友達には作曲の芥川也寸志、齋藤高順、奥村一等、ピアノの梶原 完、鈴木良一等、管楽器の萩原哲昌、早川博二等、弦楽器の北爪規世等が居た。新人の同期生は120名だった。陸軍戸山学校は三つのセクションに分かれていて、その一つは陸軍の体操指導下士官の養成、次は全国の陸軍ラッパ手の養成、あとの一つが軍楽隊なのだった。従って軍楽隊は学校の形態をとって居り、入隊者は本来は2年間、僕達の入った頃は戦時下のために短縮されて6ヶ月の生徒期間を過ごし、その間、受け持たされた楽器の演奏を始め、楽典、ソルフェージ、初歩の和声学、軍楽隊独特の記譜法等をびしびしと叩き込まれるのだった。そしてもう一つ、それは隣のセクションの体操専門の下士官に指導される体操が仲々大変だった。
入隊した日、僕は小太鼓を与えられた。芥川はテノール・サクソフォーン、梶原と奥村はオーボエ、後(のち)の「スーダラ節」の作曲者萩原はもともと専門だったクラリネットを、「夜明けの歌」等の編曲者早川は矢張りもともとの専門のトラムペットを与えられた。
だんだんに本土空襲が激しくなり、日本の敗戦が忍び寄っていた45年の春、僕達同期の120名は軍楽生徒の期間を終了して陸軍軍楽上等兵に任命された。

――ところが、僕が大汗をかいてこの馬鹿げた労働に従っている時、フリュートやピッコロの受け持ちの友達は、一握りのフリュート、ピッコロを持って、只一度壕迄走れば事が終ってしまうのである。この時程、大きな楽器を受け持たされる事は、小さな楽器を受け持つ事より随分と割りの合わぬ話だと思った事は無い。
1945年に戦争が終ってからも、その後何年かは、ティムパニを倒立させて鉄兜の上に載せて全速力で走っている團上等兵の、相当に漫画的な姿と、肉体的な苦しみを、何度も何度も夢に見た。
今はもうそんな夢を見る事は無いが、ティムパニを見ると、よくもあんな大きな物を頭の上に載せて走ったものだと我ながら感心するし、フリュートやピッコロを見ると、矢張りその時の羨ましさが尾を曳いているらしく、スマートで良いなあと思う。
このエッセイは、1983年より93年まで、「季刊ムラマツ」の巻頭言として、團 伊玖磨氏に執筆していただいたものを、そのまま転載したものです。
