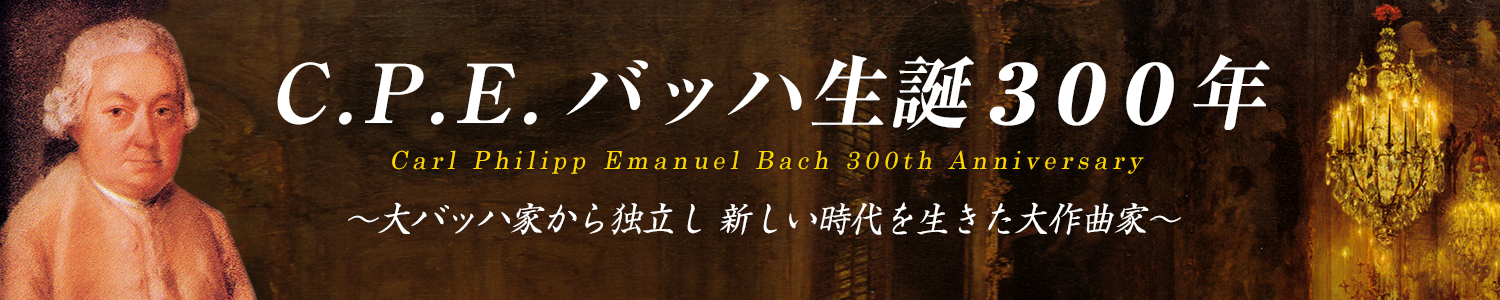白尾 隆
東京生まれ。桐朋学園大学卒業。林りり子、森 正の両氏に師事。ドイツ・フライブルク国立音楽大学に入学。オーレル・ニコレ氏に師事。1978年「特別優秀賞」を得て卒業。その後チューリッヒにおいてアンドレ・ジョネ氏に師事。
1980年〜1986年までオーストリアのインスブルック交響楽団の首席フルート奏者を務める。又ソロ、室内楽の分野においても活動、オーストリア国営放送に多くの録音を残す。
1986年帰国。1987年より「サイトウ・キネン・オーケストラ」国内外の公演に参加。現在、桐朋学園芸術短期大学特別招聘教授、武蔵野音楽大学・広島エリザベト音楽大学講師、ムラマツ・フルート・レッスンセンター・マスタークラス講師。
また、ソリストとして幅広い演奏活動を行なっている。