フルートを愛する人に、愛されるフルートを。
商品ID検索
商品や季刊誌に記載されている「楽譜ID」と「CD-ID」で商品を検索する事ができます。
メンバーズ・クラブ「フルート・インフォメーション」記載の商品番号で検索する場合は、最後のハイフン以降の番号で検索してください。
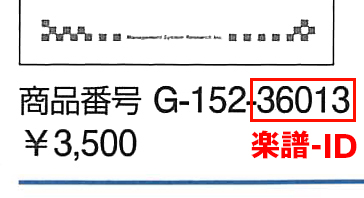
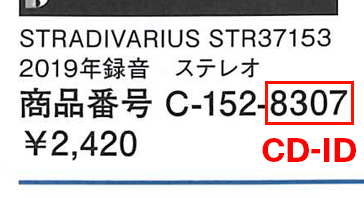
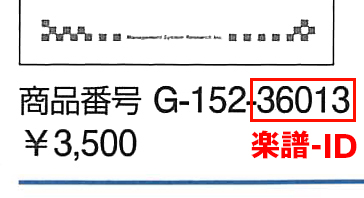
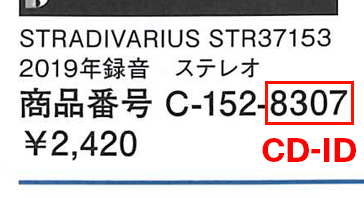
もがりぶえ
4.夕鶴とフリュート
「夕鶴」は初めからオペラに作曲したのでは無かった。オペラに作曲する前に、芝居の舞台用の演劇附帯音楽と、そのすぐ後に作った放送劇用の音楽があった。1949年の春、木下順二さんの戯曲「夕鶴」は婦人公論誌上に発表された。この作品は、戦時中に書き溜められていた「彦市ばなし」「「二十二夜待ち」等の木下さんの民話劇集の一つ「鶴女房の恩返し」を発展させた作品であったが、発表と同時に、その内容とスタイルの新鮮さ、美しさ、構成の見事さに、すぐさま珠玉の傑作の評價を得た。この戯曲の初演は同年の秋、奈良県丹波市(たんばいち・現在の天理市)の天理教本部講堂でであった。出演は、つう・山本安英、与ひょう・桑山正一以下ぶどうの会の人達だった。この初演のために附帯音楽の作曲を依頼された僕は、先ずこの雪に閉じ込められた北方の情景と寒気、澄んだ空気にフリュートの音を思い、農村の葦笛からオーボエを思い、人間の純粋性に対する物慾の世界の象徴としてファゴットの低音を思った。そして、つうが血を流して千羽鶴を織る機(はた)の音にハープを思った。構成はこうして、フリュート、オーボエ、ファゴットの木管三重奏にハープを加えた。理論的に考えた訳では無いのだが、歴史の新しいクラリネットは音色の新しさから加わらなかった。日本の笛は、御存知のように神楽笛、能管、龍笛、尺八等のような無簧管と、篳篥(ひちりき)のような双簧管はあっても、西洋でも時代が新しくなって発達した單簧管は無いために、クラリネット、サクソフォンのような單簧管は、音色的に日本的旋律を扱うには――無論、出来ないことは無いけれども、微細な感覚上の疑問が多く起こるのである。笙は発音部は單簧であるけれども、寧ろ和音楽器であって、旋律楽器では無いから、これは又少し別の話しになる。
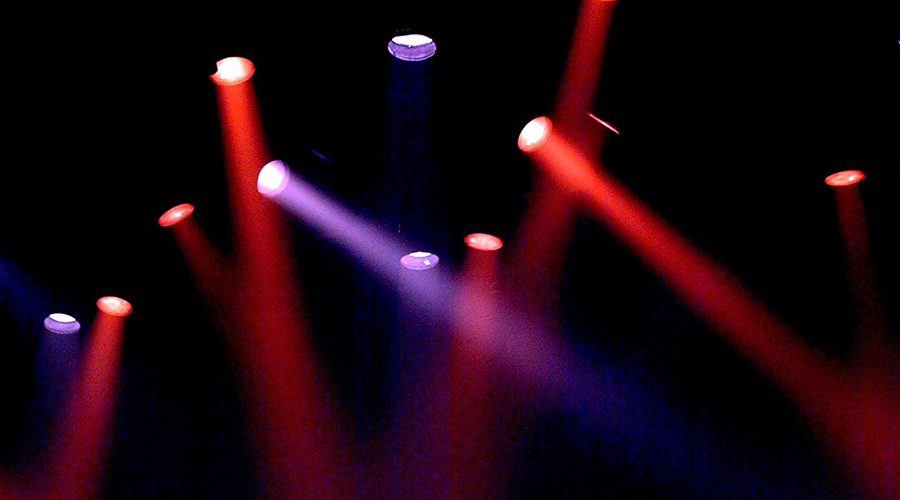
演劇への附帯音楽も、それを小管弦楽に改変した放送用の音楽も、全く姿を変えたオペラでも、冒頭の序奏が終り、雪景色の幕が上がる部分、そして随所にフリュート・ソロは大活躍をする。オペラで言えば、あれ程多くフリュートが活躍するオペラは無いであろうとさえ思う。
僕の一生の伴侶であった演劇の、オペラの「夕鶴」を思う時、僕は何よりもフリュートの音を想う。――日本の美しい雪景色、そしてそこに繰り拡げられる美しい物語りとともに――。
このエッセイは、1983年より93年まで、「季刊ムラマツ」の巻頭言として、團 伊玖磨氏に執筆していただいたものを、そのまま転載したものです。
