フルートを愛する人に、愛されるフルートを
商品ID検索
商品や季刊誌に記載されている「楽譜ID」と「CD-ID」で商品を検索する事ができます。
メンバーズ・クラブ「フルート・インフォメーション」記載の商品番号で検索する場合は、最後のハイフン以降の番号で検索してください。
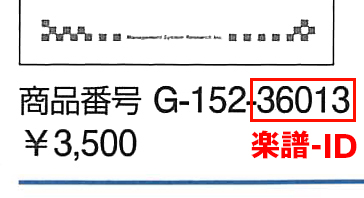
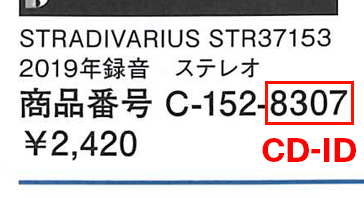
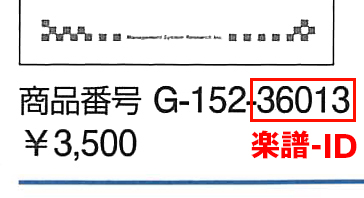
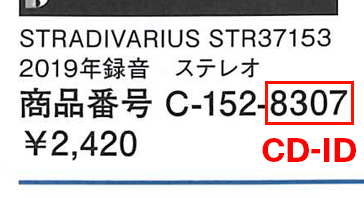
もがりぶえ
6.12本のフリュート
作曲家にとって最も嬉しい事は、書くという行為によって作品が徐々に蓄積して行く事と、一所懸命に書いた作品が演奏されて多くの方々の耳に届く瞬間であろう。その二つの喜びは、どちらがどちらと言えぬ程両方とも喜びに満ちている。第一の喜びは、作曲家を次の、又次の次の作品に向かわせる原動力になるし、第二の喜びも亦然りである。ただ、その喜びの質が、前者はやや私的で、後者がやや公的なところが違うと言えば違う。1984年は、殆ど自作の演奏ばかりに従っていた。僕の場合は自作の演奏は殆ど僕が指揮する事を依頼されるので、地方都市でのオペラ「夕鶴」の公演も例に依って続いたし、二つの割り合いに大きな合唱組曲の初演も、練習又練習と忙しかった。
演奏の山は、北京で2夜に亘って中国中央楽団を指揮して開いた「團伊玖磨交響作品演奏会」だった。曲が、管弦楽のための「夜」、管弦楽組曲「シルク・ロード」、新作初演の交響幻想曲「万里長城」、「交響曲第2番変ロ調」と皆大きく、全て中国のオーケストラには初めてだったためもあるが、練習は12日間、中国の音楽家達と僕の精神の集中力と体力の競争のような12日間だった。日本のオーケストラもこの位の練習期間を持てばもっと良い音がするようになるのにと思う。

秋もたけなわになって日本に帰って来た僕のスーツ・ケースの中には、あと清書だけを残した「12本のフリュートのための『夕鶴』幻想曲」が入っていた。
僕にとって最も嬉しい事は、書くという行為によって作品が出来上がる事と、一所懸命に書いた作品が演奏されて多くの方々の耳に届く瞬間である。この事はいつまでも変わらない。
このエッセイは、1983年より93年まで、「季刊ムラマツ」の巻頭言として、團 伊玖磨氏に執筆していただいたものを、そのまま転載したものです。
