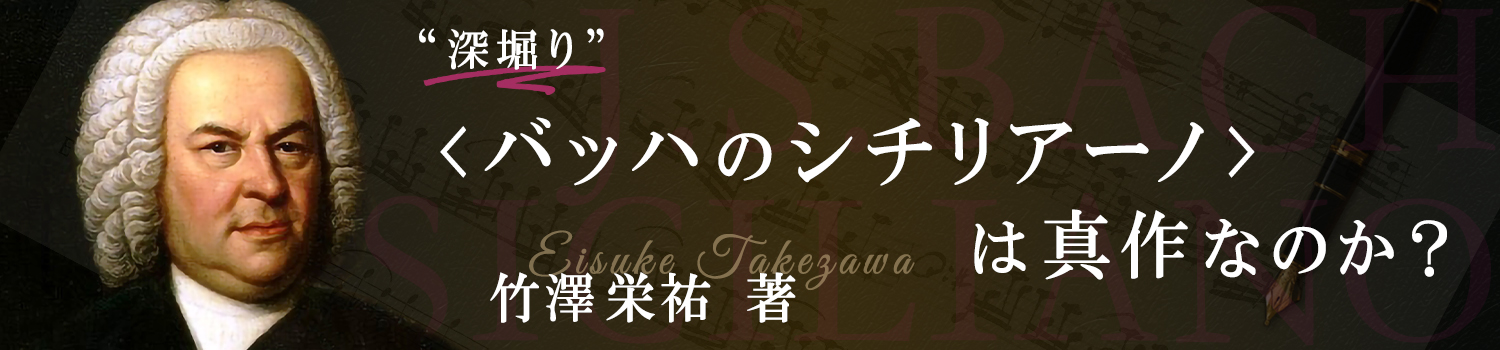「バッハのシチリアーノ」を第2楽章に持つ<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ 変ホ長調 BWV1031>。その第3楽章を、1962年に刊行されたランパル校訂版と、最も古い筆写譜とで比べてみると、ランパル校訂版にはアクセント記号が付け加えられていることに気づきます。
J.S.バッハ<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ 変ホ長調 BWV1031>第3楽章【筆写譜】
J.S.バッハ<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ 変ホ長調 BWV1031>第3楽章【ランパル校訂版】
実は、このような違いは、他のソナタでも見られます。たとえば、<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ ロ短調 BWV1030>の第1楽章では、1964年に刊行されたルイ・モイーズ校訂版とバッハの自筆譜を比較すると、モイーズ校訂版には数多くの音楽記号が付け加えられているのです。
J.S.バッハ<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ ロ短調 BWV1030>第1楽章【自筆譜】
J.S.バッハ<フルートとオブリガート・チェンバロのためのソナタ ロ短調 BWV1030>第1楽章【L.モイーズ校訂版】
なぜ名演奏家や編纂者は、わざわざ音楽記号を加筆したのでしょうか?
前回取り上げたドビュッシーの自筆譜には、多彩で繊細な音楽記号が記されていますが、それらの記号は「作曲家の意図」を明確に示していると言えるでしょう。これに対してバッハの、とりわけ器楽曲の自筆譜には、アクセントやクレッシェンドを示すヘアピン記号はもちろん、強弱を示す
f や
p といった記号もほとんど記されていません。実のところ、バッハは同時代の作曲家と比べて多くの種類の強弱記号を用いたほうでしたが、それは主にカンタータなどの声楽曲においてのことでした。器楽曲の場合、当時の楽器自体の音量が小さかったため「基本的には
f で演奏されるもの」と受け止められており、強弱記号はほとんど書き込まれませんでした。さらに、当時はまだ普及していなかったヘアピン記号やテヌート記号は一切用いられていません。
こうした背景を理解しないまま、後世の演奏家などが加筆した音楽記号をバッハが残したままの姿と受け止めてしまうと、解釈を誤る危険があるのです。
では、アクセント記号やクレッシェンド、ディミヌエンドを示すヘアピン記号が一般的に用いられるようになったのは、いつ頃からでしょうか?
この問いに答えるため、拙著『<バッハのシチリアーノ>は真作なのか?』の第4章ではアクセント記号に焦点を当て、その歴史や演奏法について詳しく解説しています。
たとえば、エネスコの<カンタービレとプレスト>には、作曲家自身によると思われる豊富な音楽記号が記されています(自筆譜が公開されていないため断定はできません)。
エネスコ<カンタービレとプレスト>【Enoch版】31〜39小節目
一方、20世紀以降に刊行されたバッハの楽譜には、前述したランパル校訂版やルイ・モイーズ校訂版のように、名演奏家や編纂者によって補筆されたものが少なくありません。こうした楽譜には、バロック音楽の専門知識がなくても演奏に取り組みやすくなるように、さまざまな音楽記号が加筆されています。しかし同時に、そうした記号が必ずしも作曲家本人の意図を反映しているとは限らない、という問題も抱えているのです。
見た目にはよく似ていたとしても、作曲家の手によるものか、それとも後世の加筆かで、その意味合いは大きく異なります。しかも厄介なことに、楽譜を眺めただけでは、その違いを見分けるのは容易ではありません。
このような問題を解決するために刊行されたのが、私の師でもある<パウル・マイゼンの解釈による W.A.モーツァルト作曲 フルート協奏曲ト長調 KV313・ニ長調 KV314>の楽譜です。ご興味のある方は、本ホームページの記事アーカイブにある、
拙稿「日本・オーストリア友好150周年特別企画 W.A.MOZART」第3回 をご覧ください。
<パウル・マイゼンの解釈によるW.A.モーツァルト作曲フルート協奏曲ト長調 KV313・ニ長調 KV314> ※現在、絶版です。
<パウル・マイゼンの解釈によるW.A.モーツァルト作曲フルート協奏曲ト長調 KV313・ニ長調 KV314>【注釈】 ※現在、絶版です。
この楽譜では、マイゼンによる補筆部分が赤で印字されているため、原典版との違いがひと目でわかります。さらに解説や注釈も添えられていて、どうしてそのように補筆されたのか、そして演奏解釈の「根拠」まで理解できる仕組みになっています。
「根拠」ある演奏を目指して
幼児は、親の口まねから言葉を覚えます。これは誰もが通る学習の過程です。同じように、YouTubeなどで気軽に音楽を聴くことができるこの時代に、ある名演奏家の演奏を真似することも、曲をマスターする近道になるかもしれません。しかし、人はやがて親から学んだ言葉を使って、自分の意思を自分自身の言葉で相手に伝えるようになります。演奏も同じです。名演奏を聴いたとき、「なぜこの場面でクレッシェンドしたのか」「なぜこのような表現をしたのか」といった理由は、本人に直接聞かなければ分かりません。つまり、うまく真似することはできても、その演奏の根拠は不明なままです。根拠がない演奏は説得力を欠くだけでなく、決して自分の意思による表現にはなりません。
“Good artists copy, great artists steal.”
と画家パブロ・ピカソは語っています。
ここでいう「盗む」とは、単なる真似ではなく、他者のアイデアを自分の中で消化し、新たな表現へと昇華させることを意味します。
では、演奏に根拠を与えるにはどうすればよいのでしょうか。
その一助になるように、『<バッハのシチリアーノ>は真作なのか?』を書きました。
一曲を深く理解し、そして演奏するには、その曲が生まれた時代背景、作曲家の生涯や人物像、遺された他の作品、さらに同時代の作曲家の作品など、幅広い知識が必要です。こうした探求に終わりはありませんが、少しずつ知識を積み重ね、バッハの作品についての理解を深めることで、最終的には「<バッハのシチリアーノ>は真作なのか?」という問いへの答えに近づくことができるのです。
つまり、「根拠ある演奏」とは、作曲家の意図を見極め、楽譜の背後にある歴史や背景を理解し、さらに自分の解釈と融合させた演奏のことなのです。
音楽記号を読み解くキーワードの一つは「多義性」
ドラマ『舟を編む〜私、辞書を作ります〜』第1話では、「なんて」という言葉が文脈によって異なる意味を持つことが描かれていました。たとえば、「なんて美しい」の場合は肯定的な意味に、「私なんて」の場合は否定的な意味を表します。同じ言葉でも、使い方や状況によって意味が変わる。これが「多義性」です。
音楽記号にも、この多義性が存在します。
たとえば、ある音にアクセント記号が付いているからといって、いつも金づちで打ち込むような鋭いアタックを求められているわけではありません。記号の意味を理解するにも、その曲の生まれた時代背景や作曲家の意図、そして音楽全体の文脈を考慮することが重要です。
記号をただ機械的に読むのではなく、メールに添えられた絵文字のニュアンスをくみ取るかのように、その背後にある意図を探りながら表現につなげていく。そうした思索を重ねることで、演奏に確かな根拠が生まれます。そして、まるで親の言葉を真似て学習していた幼児が、自分の言葉で話し始めるように、演奏もまた音楽記号をただ物理的に音にする段階から、自分自身の表現へと育っていくのです。
このWEB連載では、前回はカラー画像を、そして今回からは動画を用いて、本だけでは伝えきれない内容をさらに深掘りしていきます。めざすのは「飛び出す絵本」ならぬ「音の出る本」です。今回は、フルートとピアノによる演奏動画で、アクセント記号の多義性や解釈の広がりを体験してください。
VIDEO
【第3回 音楽記号について深掘りする】実際の楽曲を取り上げながら、楽譜に記された記号にどのような解釈の余地があるのかを考えてみましょう。Fl.解説 竹澤栄祐、Fl.亀田 尚大、Pf.東浦 亜希子