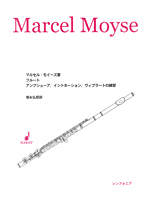楽譜ID:12154
オペラ作品や様々な楽曲を収集し、オペラ歌手や弦・管楽器の奏法を模倣することでフルートのテクニックにどの様に結びつけるか等、果てしない研究を続けてきた内容がこの教則本より読み取る事ができます。また「トーン・デヴェロップメント」や「ソノリテについて」がどのように考えられたか等の内容も書かれています。モイーズが美しい音を奏でるために努力を惜しまず、常に「音楽」と向き合っている姿勢は何度読んでも胸が熱くなります。モイーズ自筆のカリグラフィと有馬茂夫氏訳、吉田雅夫氏監修による日本語訳付き、巻末にはオペラ作品などから集めた譜例集と低音域と広い音域の跳躍の練習曲が付いています。ぜひこの教則本からモイーズが生涯研究し続けた「美しい音」への追求心を感じて下さい。