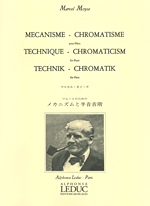楽譜ID:2359
| 奏 法 | 音/音程/音階/分散和音 | ||||
| 難易度 | 初心者 | 初級 | 中級 | 上級 | 最上級 |
「ソノリテについて」の予備基礎練習で、低音域から中音域、中音域から高音域とすべての音に触れられるように考えられています。また初級者のために調号を使わず臨時記号で書かれているため調号に気を取られることなく、音づくりに集中して取り組めるよう配慮されています。奇数ページは応用練習になっていますが、学習者の呼吸状態や練習時間などに合わせて偶数ページの練習だけでも良いと書かれています。「ソノリテについて」が少し難しい方はこちらの教則本がおすすめです。初めて出会う「音」を大切にした教則本です。