���iID����
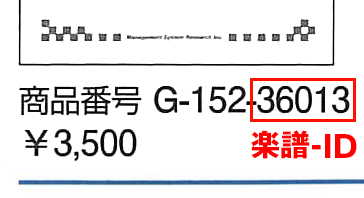
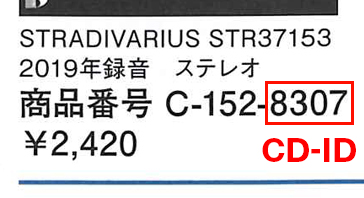
�����p�K�C�h
�}�C�y�[�W
���i����
�J�[�g������
���iID����
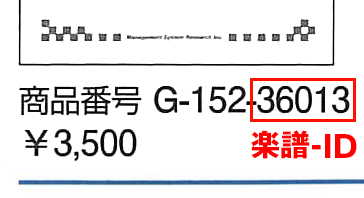
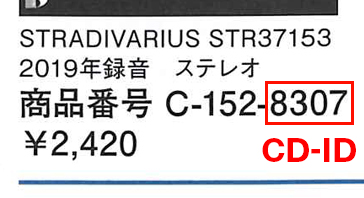
���i����
����̓A�i���[�[�̗\���m���Ƃ��đg�ȂƔ{���Ɋւ��Đ������܂��B
�o���b�N���ł́A�u�g�� Suite�v�Ƃ������̂̓\�i�^�ȑO����g���Ă������̂ŁA�قڃ\�i�^�Ɠ������̂������B�\�i�^�͋���\�i�^�Ǝ����\�i�^�i���Ȓ��S�̍\���Ő����I�ł���Ƃ��������狳��ł͉��t�ł��Ȃ����́A����͕��ȍ\���̑g�Ȃ����l�j�ɕ��ނ���Ă�����17���I�ɂ��̈Ⴂ������ɞB���ɂȂ�A�g�Ȃ̕��̓R���Z�[���A���ȁA�p���e�B�[�^�ȂǗl�X�Ȗ��̂ƌ`���ŏ������悤�ɂȂ�BJ.S.�o�b�n�͑g�Ȃ̊�{�`�Ƃ��ăv�������[�h�A�A���}���h�A�N�[�����g�A�T���o���h�A���k�G�b�g�i�u�[��/�K���H�b�g�j�A�W�O�[�̍\����蒅���������A�t�����X�ł͗Ⴆ�v�������[�h��14�ȂƂ��N�[�����g��4�ȂƂ��A�t�����\���E�N�[�v�����ł͑g�Ȃ̎����I�[�h�D���iordre�����ԁj�ƌĂ�ŁA���ɂ�23�ȍ\���Ƃ������̂��������B�����Ď���Ƌ��ɕω����A���}���h����ł͕��䉹�y���甲�����ďW�߂��Ȃ��u�g�ȁv�Ƃ��鎖�������Ȃ�A�t�����X�ł͕����푈��A�t�H�[���̉�ŏ������悤�ɍ������y����̗��O�A�t�����X�̌|�p�iArs Gallica�j���咣���邱�ƂŁA�ĂуN�[�v����������̃X�^�C���Ɋ�Â��\���������Ȃ����B
�o�b�n�������Ɛ́A�A���}���h�A�N�[�����g�������܂Łu�x��v����������A����2�͘A�������x�肾�����B�A���}���h��2���q�ɑ��Ă����3�������邱�Ƃ�3���q�ɂȂ葬���X�e�b�v�̗x��ɂȂ�B���ꂪ����o���b�N�̑g�Ȃł͓Ɨ�����2�ȂɂȂ����B�����Ń|�C���g�ɂȂ�̂��{�����Ȃł���̂ŃX�e�b�v�̓��ݍ��݂̂��߂̈���������O�ɂ���Ƃ������B���́u�͂��߂̈���v���u�A�i�N���[�Y�v�Ȃ̂ł���B���Ƃ���ƌ��X�A���}���h�ƈ�̂ő����Ă����N�[�����g�ɂ���ɃA�i�N���[�Y������B�łȂ���Δ�������Ȃ��ĂȂ���悤�������B�܂�A�y���ɃA���}���h�A�N�[�����g�Ə�����Ă��Ă��i�J��Ԃ��̗L�������f�v�f�����j�A�i�N���[�Y��������Ζ{���Ⴄ�Ȃ������\����A���}���h�ƃN�[�����g�̊W�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��A���邢�͏o�Œi�K�ł����Ăɕt����ꂽ���O�ƍl����̂��A�i���[�[�ł̏펯�ł���B
��i�̒��̉��K��a�����{����̉e��������{����𗘗p�����肵�Ă���ꍇ������B���̂�������A�i���[�[�̑ΏۂƂȂ�B��ȋZ�@�ɔ{���T�O�����������̂�20���I�ɓ����Ă��炾���A�A�i���[�[�I�ɂ݂�ƃo���b�N������{���W�ɂ���Đ��ݏo���ꂽ��ȋZ�@�͑��݂���B
��̉����̉�������̉��g�̎��g���̐����{�̎��g�������R�ɔ�������B
�t���[�g�̏ꍇ�ŏ��̃I�N�^�[������Ƃ��āA��2�A��3�I�N�^�[���͔{�����g���Ă���̂͒N�����������Ă��邪��ɂ����R�{���͂��łɊ܂܂�Ă���B
20���I�Ȍ�̍�ȉƒB�̔{���Ɋւ��鋤�ʂ����T�O�́A�Ⴆ�� C�̔{����\����G�AE�AB�AD�AFis��C�ɑ��đS�ċ��a���W �ł���A���̉��ǂ����̑g�ݍ��킹�͘a���_�I�ɕs���a���������Ƃ��Ă����肵�������ȋ����������炷�̂ŋ��a���ł���Ƃ����l�����B
�ł͔{���̑��݂́A�Ȃ̒��łǂ�Ȏ��ݏo�����̂��B
�O�o�́u�{����\�����͋��a���v�Ƃ����������炷��ƗႦ��C-dur�̎�a��C�AE�AG�͍����̔{����̒�{����̍\��������c-moll�ł�C�AEs�AG�ƂȂ荪��C�̔{����ɂ͂Ȃ�Es�����鎖�ɂȂ���肵�������ɂ͂Ȃ�Ȃ��ƍl����B�o�b�n�⑼�̃o���b�N�̍�ȉƂ����͊��o�I�ɂ���������Ă����̂��낤�B���Ƀo�b�n�ɂ����Ă͒Z���̋Ȃ̏I�~�ɂ����āA�Ⴆ���ꂪ�I�Ȃł���ꍇ�⎟�̊y�́i���͒����j�Ƃ̃n�b�L�������藣�����l���Ă���ꍇ�A�Ō�̘a���̑�3�����グ�Ē����ɂ���A������s�J���f�B��3�x���g�p���邱�Ƃ������B�s�J���f�B���g��Ȃ��ꍇ�͑�3���i�Ƒ�5���j���ăI�N�^�[���ŏI�~����B��������Ί��S���a���̈��肵��������������B
�����18���I�̍�ȉƃW����=�t�B���b�v�E�����[�̗��_���ɏ�����Ă������̂Ńg�j�b�N�ƃT�u�h�~�i���g��3�a���ɍ����̒�6�x������t������Ƃ����l�����BC-dur�g�j�b�N�Ȃ��C E G A�ɂȂ���A�����A C E G �̑�1�]��`�Ƃ͍l�����A�����܂�6�x�̕t���ƍl����B������O�o�Ɠ����Ŕ{���ōl�����C�������Ƃ���C E G�͋��a���AA�������Ƃ���A C E�́A�s���a���ƂȂ艹���I�ɈႢ������B���̎�@�̓h�r���b�V�[�ɂ��g�傳��A�����F���͂���ɔ��W�����đ�7�A��9�ւ̕t���A����ɒZ6�x�����̕t�����g���Ă���B�S�[�x�[���̍�i�ł�����������B
�אڂ���ቹ�i�������j�������ɋ��������ɁA���̏�ɂ��ꂼ��̔{����Ɋ܂܂�鉹���������Ė炷�Ƃ�����@�B�T�^�I�ȗႪ�u���m�X�̉́v�ŁA�ŏ��̕����̉��̑S�Ă̓s�A�m�̃o�X��G��As�̔{���݂̂ŏ�����Ă���B�S�Ă���̉��������a����ԂȂ̂ł��̒��œ����t���[�g�̑����p�b�Z�[�W�͕K�R�I��32�������̍����t���[�[�̕K�v��������A�J�f���c�@���ɂ�����肩�瓮���Ȃ�ĉ��t�͍�Ȃ̈Ӑ}�Ƃ͑S����������Ă���B
��V������=�}���[�E���B�h�[�� �g�� ��i34��
�\����͈ꌩ4�y�̓\�i�^�Ɍ����邪�e�Ȃ̌`���͗l�X�ŁA�S�̂Ƃ��ă\�i�^�̌`�Ԃɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��B�����I�Ȃ̂͑�1�Ȃ̃��f���[�g��4����2���q�A��2�Ȃ̃X�P���c�H��8����3���q�ŁA�����Ƃ��A�i�N���[�Y����n�܂�O�t���������B���̔��q�̊W�ƃA�i�N���[�Y�ɂ��Ȃ���́AJ.S.�o�b�n�ɂ�����g�Ȃ̃A���}���h�ƃN�[�����g�̊W���̂��̂ł���B��������ƃ��}���X�̓e���|�I�ɂ̓T���o���h�ɑ�������悤�ł͂��邪�A����̓x�[�g�[���F���Ȍ�悭�g���Ă���������u���}���X�v�ƍl������B4�Ȗڂ�Final�Ƃ����薼���ӂ��킵�����낤�B����܂Ńt���[�g���ȁ����ň����Ă����p�����y�@���Ǝ����ۑ�ȂƈႤ�̂͑������ɂ��Έʖ@���g���Ă���_�B����ɂ���ĈႤ�����f�B�[���t���[�g�ƕ��s���Ĉꏏ�ɓ�������A3�x�����ŏd�Ȃ��Ă�����A�t���[�g�����t�ɂ܂������Ƃ����l�ȁA�������Ƃ̃A���T���u���̗v�f�������Ȃ��Ă���B
���B�h�[���̂��̍�i�̍ő�̓����́A�u�����v�Ƃ��Ẵy���I�h���ӂ�Ɏg���Ă���_�B���t���Ă݂Ă����ɋC���t���̂́A�Z�߂̃J�f���c�@���p�b�Z�[�W��������ݍ��܂�Ă���Ƃ������B����̓J�f���c�@�ƌ������́u�������܂ꂽ�������`�v�ƍl����ׂ��ł���B���B�h�[���͑����̖���ł���I���K�j�X�g�Ƃ��Ċ������̍�i���B
���ƌ����Ă���ۓI�Ȃ̂��Ȃ̖`���̒Z���O�t�A���Ƀs�A�m�̉E��̍�������ł̃I�N�^�[�������͓I�ɋ����B���̕����p�b�ƌ��ɂ̓��m�X�̖`���ƕ��ʓI�Ɏ��Ă���B�W�������F�̃h�D�[�u���E�o�X�́A�����܂Ńo�X�̋����Ƃ��̏㐺���̊W�Ȃ̂����A���̃s�A�m�̉E����h�D�[�u���E�o�X�ƌ��Ȃ����������̔{���ł͓����l�ȊW�����Ă͂܂�B���̈�ۓI�ȋ����͂��炭���̒��ŋ��������銴�o������B����ɑ����e�[�}�̃����f�B�[�̓��}���h�I�ȕ��ʂ̃����f�B�[���C�������A���̃����f�B�[���܂߁A�s�A�m�E��̓�����16���������S�Ẳ���As��G�̔{���ɑ����i5����1���ڂ̃E����Des���o�Ă��Ă����œ]������܂Łj����B���̂��߂��Ȃ莩�R�ȓ����̓������`���������R�ɋ����̒��Ɉ��肵�ėn�����ށB�I���K�j�X�g�Ƃ��ĕ��G�Ȕ{���̒��ɐ�������ȉƂ̓Ɠ��Ȋ����ł���A�W�������F�̃h�D�[�u���E�o�X���70�N���O�Ɋ��o�I�ɓ����o������ȋZ�@�ł���B�\���Ƃ��Ă͊�{�I�ɃZ�N�G���c�B�A�`���ŁA�t���[�Y��2��J��Ԃ����B
��2�ȃX�P���c�H�������I�ȒZ���O�t�����B���x�̓I�N�^�[����H�݂̂ŏ�����Ă���B�\���I�ɂ̓s�A�m�̃I�N�^�[���Ƀt���[�g�����j�]���ŏd�˂Ă���A�I���K���ɗႦ��Ȃ�I�N�^�[���E�X�g�b�v�ƃt���[�ǃX�g�b�v�g�p�̋������B���t�`�́A�R���g���^���Ŏ~�܂�C�A���u�̃��Y���̃��Y���y�_���A�t���[�g�̃����f�B�[�̓g���V�F�[�̃��Y���A�t���[�g�͓r������16�������̉��s�`�̘A���ɂȂ邪�����ł͂킸���ȓ]�����A������B�t���[�g���g���V�F�[�̃y���I�h���e�[�}A�A16�������̃y���I�h���e�[�}A�̃R�}���e�[���B���Ƀs�A�m�E�肪�t���邽���Ղ�Ƃ��������f�B�[���e�[�}B�ŁA�����ł̓t���[�g�̃A���y�W�I�ɂ�����ꂽ�X���[�ƃs�A�m����̃C�A���u�̏�s�A���y�W�I�A�E��̓w�~�I���ƂȂ�|�����Y���I�ȑΈʖ@���\������B�ĂёO�t��1���オ���Č���A���g����U�����A���ɖ߂��ăe�[�}A�A�e�[�}B����R�[�_�Ɏ���B�`����2���`���B
��3�ȃ��}���X��3���ŏ�����Ă��邪�o���b�N�̃g���I�E�\�i�^�ɋ߂����@�ƍl������B�ŏ���As-dur�̃h�~�i���gEs�̃I�N�^�[���������e�[�}A���t���[�g�Ɍ����BEs�̃I�N�^�[���͂����Ƀs�A�m����Ɉڂ�A�ʑt�ቹ�I�ȃo�X�A�I�N�^�[�����d�˂�Ƃ�����I���K���̃y�_����16ft�X�g�b�v�̗l�ł���B30���߂���e�[�}A�̃R�}���e�[�����n�܂邪���̃y���I�h�ł͂��̃R�}���e�[���̃t���[�Y����ɂ����e�[�}B�ƂȂ��ĕω��ɕx�������t���y���݁A���̌�Ƀe�[�}A���Č�����B�e�[�}B���e�[�}A�Ƃ́A���ɑ������ƌ����_�Ő��i���قȂ�R���g���X�g�����ĂȂ̂�3���`���ł���B
�s�A�m�̃A���y�W�I�ɂ��4���߂̃f�R�iDécor�j����t���[�g�ɂ��e�[�}A���n�܂�A15���߂ŒZ������������Ńe�[�}A�̃R�}���e�[���������B�R�}���e�[���ł͓����ɃA���y�W�I���ێ����A�o�X�ƃt���[�g���ΐ�����2��J��Ԃ��i�Z�N�G���c�B�A�`���j�t���[�g���㐺���y�_���܂ŏ㏸����ƃs�A�m�̉E��ƍ���ɑΐ������ڍs���A����Ƀh�~�i���g�ֈ�C�ɍ��g���ăt���[�g�̑������`�ŏI�~����B30���߂���̓e�[�}B�A38���߂���̓e�[�}B�̃R�}���e�[���A�Ō�Ƀe�[�}A�̃��`�[�t���g�������ڕ����o�ăe�[�}A���Č�����B79���߂���Es-dur�ɓ]�����e�[�}A�̃R�}���e�[���̃����f�B�[����h�������e�[�}C��������n������Ȃ���ϑt���J��Ԃ��A�s�A�m�̑������`���͂���ŁA�e�[�}A�̃��`�[�t�̓W�J���n�܂�B147���߂Ńe�[�}A�ɖ߂�A�e�[�}C�iB�̔h���j�̃����f�B�[������A�t���[�g�͑S�ʓI�ɑ������`�����t����B�����ł������̓n��������N���邪�����f�B�[�̓I�N�^�[����������3�I�N�^�[���̃��j�]���ŁA�I���K���Ȃ��4�A2ft�X�g�b�v�ʼnE��Ō���3�i���𑀍삵�y�_����16ft���g���Ƃ����\���ɂȂ��Ă��Ă�����I���K���I�ȏ��@�̃t���[�g�̋Ȃ͑��ɖ����B�Ȃ̌`���̓����h�\�i�^�`���ł���B
���̋ȂɊւ��Ă̓s�A�m�����܂߂Đ����̊W��c�����鎖���܂��d�v���Ǝv���܂��B�ȑO�V���~�i�[�h�̑Βk�ŃA�i���[�[�ł̌`���_������������A���t���邽�߂̒n�}�̗l�Ȃ��̂��o����ƌ����܂������A�Έʖ@�������Ƃ����ɉ����ɂ�鐂�������̗��̓I�ȃ��[�g���ł��A���ꂼ��̃��[�g��F�l�B�������Ƃ����������ɂȂ�܂��B���X�ꏏ�ɂȂ�����Ⴄ���[�g�ɔ�шڂ�����Ƃ������ɂȂ��ł��B�\�Ȍ��葼�̐������A�A���T���u�������Ă����̂��|�C���g�ł���y���݂ɂȂ�܂��B�������`�ł̃t���[�[�͉��t�Z���X�����镔���ł���A���ƌ����Ă������ȓ]��������̂����ł��B�܂��͓]�����ɍ���łƂ肩�����������ǂ��ł��傤�B���̓��B�h�[���͏o�ł���Ă��܂��������̊y���ɑ��āu����ς�t�H���e���s�A�m�ɂ��ė~�����v�Ƃ��u���̉���3�x�����v�Ƃ��ύX��v�����鎖���������悤�ł��B������ł͋����ɒ��t�����������̂ŕύX�͕s�Ȃ̂ł����A����ł��ύX�������Ƃ����b���c���Ă��܂��B�܂�1�y�[�W���ۂ��ƒ��蒼�����������Ƃ������ł��B�t�H�[���ł�����Ȏ��͋��ۂ��ꂽ�̂Ɂc��͂�u���炢�v�̂ł��B�]���ă��B�h�[���̊y���͂قڃ~�X���Ȃ��ƍl���ėǂ��̂ł�������́u�t�B�����c�F�g�ȁv�̏��Ŋy���ł̓~�X������������܂����B1919�N��ꎟ���E���I������̊y���Ȃ̂Ŏd�����Ȃ���������܂���B
���B�h�[����1��ŏ����܂������g�ȁ@��i34�͌��݂̊y���i1898�N�j�Ə��Łi1891�N�j�ňႢ�܂��B�܂���1�Ȃ�94���߂���113���߂̃s�A�m�̉��`���ύX����Ă��܂��B��4�ȁAFinal�ł́A��2���̃s�A�m�̍���Ő������lj�����A�W�J����Tranquillamente�̕\���͏��łł�Poco meno vivo�ɂȂ��Ă��܂��B�Č����ȍ~�͋Ȃ̏I���܂ő啝�ɕύX����Ă��菉�łł͍Ō�̕��̃t���[�g�̃p�b�Z�[�W�͑������`�ƌ����قǂ̕��ł͂���܂���B���̕���1898�N�łł͂��Ȃ��Փx���オ���Ă���A�����|�I�ɔh��ȋȑz�ɕύX����Ă��܂��B�O�o�̗l�Ƀ��B�h�[���͏o�łɊւ��Ă��u���ł��ł����v�Ƃ����1898�N�̏o�ňȌ���ύX����\���͂������킯�ł����B�������Ȃ������Ƃ������͂���1898�N�ł����S�����`�Ƃ������Ō��݂̊y���ł̉��t�Ɋւ��āu���̋Ȃ�1898�N��ł���v�Ƃ��ėǂ��Ǝv���܂��B��������ƁA����1898�N�Ƃ����N�Ƀt�H�[���̃t�@���^�W�[�����܂ꂽ�����l����ƃ��B�h�[���ƃt�H�[���̊W���܂߂ċɂ߂ċ����[�����ł��B�����N�ɂ�����̖��Ȃ�2�Ȑ��܂ꂽ�̂ł��B�Ⴂ���T���V�����s�X�œ]��������J��L���Ă���2�l�ł��B�ύX���ꂽFinal�㔼�����̃��B���g�D�I�[�]���A�_�C�i�~�b�N���̓t�H�[���̃t�@���^�W�[�ɑR���ď���������!!�c�c�c�Ȃ�ď���ȉ����͂ǂ��ł��傤���H
�j���[�X
�֘A�T�C�g